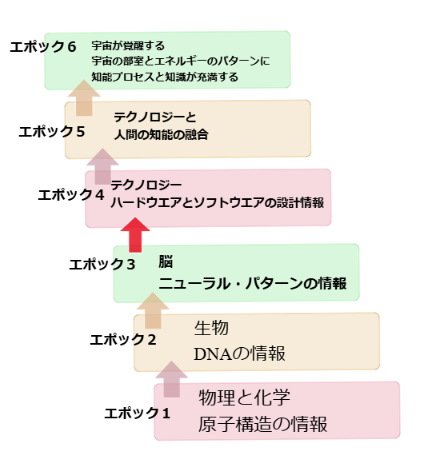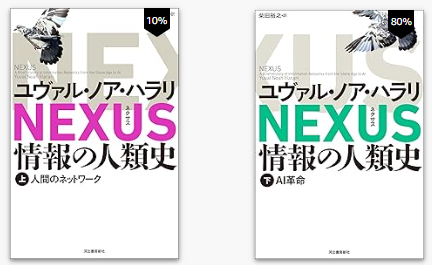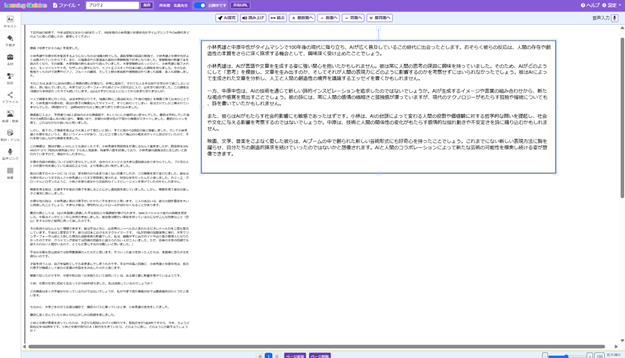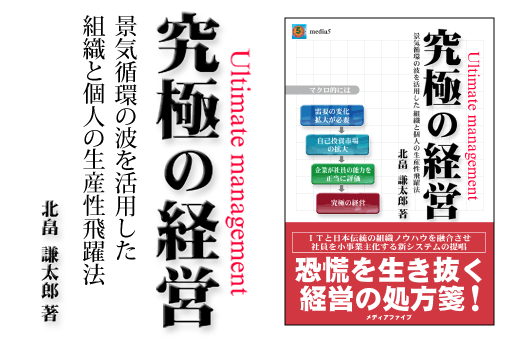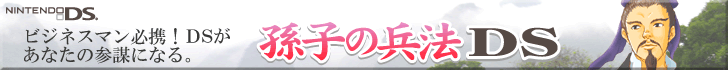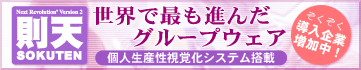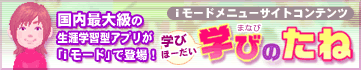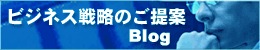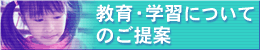小林秀雄や中原中也を愛読するようになったのは15歳の時でした。高校受験の国語の勉強で、小林秀雄と中原中也がよく出題されていたからです。また、川端康成や立原道造も高校の受験勉強で好きになりました。受験勉強の影響で本を読みたくなり、その結果、大学受験の時も本ばかり読んでいました。大学受験時はもっとひどく、小林秀雄に魅了されると、モーツァルトやドガ、セザンヌに夢中になり、ドフトエフスキーや日本の能にも興味を持ちました。そのため、勉強そっちのけで読書やピアノ、フルートの練習、そして上野の美術館や博物館ばかり通った結果、浪人も経験しました。
そのころは,あまりに自分の関心と周囲の関心が異なり、非常に孤独で、それでも人生を芸術や文学の中で過ごしたいと思い、思い悩んでいました。大学ではワンダーフォーゲル部とジャズ研究会に入り、山を登り続けました。ピアノとフルートの演奏は15歳から半世紀たった今でも続いています。(山はさすがに社会人になってからあまり登りませんが)
一人で映画を見に行くのも、ほぼ半世紀ぶりです。16歳の時に三島由紀夫の『午後の曳航』を映画で見て以来のことです。小林秀雄や中原中也、長谷川泰子の映画なんてマイナーで、すぐに終わってしまい、夜は立川でしか上映されていませんでした。1時間かけて、20時40分からの上映にぎりぎりで滑り込みました。
映画館に入ると、予想通り100人収容の小さな映画館で、5人くらいしか観客はいませんでした。最初は予約していた後ろから5番目の真ん中の席に座り、薄暗い中で、京都の中原中也の下宿から映画がスタートしました。最初のシーンを見て、これはなかなか良いなと思いました。
しかし、見下ろして映画を見るよりも見上げて見たいと思い、すぐに前から2番目の席に移動しました。そして小林秀雄と中原中也というと、酒というイメージがあり、コンビニで買った八海山の小瓶をポケットに忍ばせていたので、それを取り出しながら映画を見ました。
この映画は、題材が難しいのにとても良かったです。小林秀雄を岡田将生が演じるなんて驚きましたが、岡田将生はNHKのドラマ『昭和元禄落語心中』でも名人落語家、有楽亭八雲を好演しており、小林秀雄の講演は志ん生に近いと言われていますので、適役かもしれません。
中原中也役の俳優については知りませんでしたが、自分のイメージとは大きな違和感はありませんでした。『火宅の人』の中原中也を演じていた真田広之よりは、より実像に近い気がしました。
長谷川泰子のイメージについては、学生時代からあまり良くない印象でしたが、この映画を見て変わりました。彼女は中原中也という天才詩人と小林秀雄という天才思想家に愛される、特別な女性だったんだと感じました。カミーユ・クローデルとロダンのように、小林と中原も彼女から芸術的なインスピレーションを受けていたのかもしれません。
映画を見る前は、広瀬すずが長谷川泰子を演じることに少し違和感を感じていました。しかし、映画を見て彼女の美しさと演技に感心しました。
中原中也の詩は、小林秀雄と長谷川泰子がいたからこそ生まれたと思います。二人の出会いは、彼らの創作意欲を大いに刺激したことでしょう。大きな才能は、理性的なコントロールが効かなくなることがあります。
最近の例としては、K2の未踏峰に挑戦した平出和也と中島健郎が挙げられます。NHKスペシャルで彼らの挑戦を見ました。中島はインタビュー中に突然泣き出しました。彼自身は暖かい家庭を持っているのになぜこんな危険なこと(登山)をするのかと疑問に思って涙したのです。
その気持ちはなんとなく理解できます。彼は平出と共に、山岳界のノーベル賞と言われるピオレドール賞を二度も受賞しています。平出は三度受賞です。彼らは日本における天才クライマーです。(私が同郷の加藤保男に憧れ、大学でワンダーフォーゲル部に入部した理由も加藤保男の影響でした。私は、就職せずに山のガイドや山小屋の管理人になりたかったのですが、クライミング技術では同期の同級生に超えられない人が二人いました。ただ、田舎の大学の同期でも超えられない人間がいるので、とても仕事にするのは難しいと思いました。)
平出も中島も登山技術では世界最高峰の人たちだと思います。そういった能力を持った人たちは、未踏峰に登らざるを得ないのです。
才能を持つ人は、自己を犠牲にしても突き進んでしまうものです。平出や中島と同様に、小林秀雄と中原中也は、長谷川泰子が触媒として彼らの至高の作品を生み出したのだと感じます。
映画で知ったのですが、中原中也の詩「お太鼓たたいて笛吹いて」は、ある郷土歌に影響を受けているようです。
小林、中原の文学に初めて出会ってから50年経ちました。私は成長しているのでしょうか?
この映画は多くの予算がかかっているわけではないでしょうが、私が今まで見た映画の中では最高傑作のひとつだと思います。
ちなみに、最初の大学の研究室のゼミ合宿は鎌倉で、鎌倉のバスに乗っているとき、小林秀雄の逝去をしりました。
鎌倉に長く住んでいた小林とのなにがしかの因縁を感じました。
小林と中原が青春を送っていたのは、大正から昭和にかけての時代です。昭和元年が1925年ですから、今年、ちょうど昭和元年100周年です。小林と中原が現代のAI時代を生きていたら、どのように感じ、どのように行動するでしょうか?
そこで、当社のラーニングスケルトンAIの新コネクトシートを使って、下記のように質問してみました。
「下記内容(上記ブログ)の続きで、今年は昭和元年から100年たって、100年前の小林秀雄と中原中也がタイムマシンで今のAI時代をどのように感じ行動したか、推察してください」
そうしたら以下の解答が帰ってきました。
小林秀雄と中原中也がタイムマシンで100年後の現代に降り立ち、AIが広く普及しているこの時代に出会ったとします。おそらく彼らの反応は、人間の存在や創造性の本質をさらに深く探求する機会として、興味深く受け止めたことでしょう。
小林秀雄は、AIが言語や文章を生成する姿に強い関心を抱いたかもしれません。彼は常に人間の思考の深淵に興味を持っていました。そのため、AIがどのようにして「思考」を模倣し、文章を生み出すのか、そしてそれが人間の表現力にどのように影響するのかを考察せずにはいられなかったでしょう。彼はAIによって生成された文章を分析し、人工と人間の創造性の境界を議論するエッセイを書くかもしれません。
一方、中原中也は、AIの技術を通じて新しい詩的インスピレーションを追求したのではないでしょうか。AIが生成するイメージや言葉の組み合わせから、新たな視点や感覚を見出すことでしょう。彼の詩には、常に人間の感情の繊細さと孤独感が漂っていますが、現代のテクノロジーがもたらす孤独や接続についても、詩を書いていたかもしれません。
また、彼らはAIがもたらす社会的影響にも敏感であったはずです。小林は、AIの台頭によって変わる人間の役割や価値観に対する哲学的な問いを提起し、社会や文化に与える影響を考察するのではないでしょうか。中原は、技術と人間の関係性の変化がもたらす感情的な揺れ動きや不安定さを詩に織り込むかもしれません。
映画、文学、音楽をこよなく愛した彼らは、AIブームの中で創られた新しい芸術形式にも好奇心を持ったことでしょう。これまでにない新しい表現方法に胸を躍らせ、自分たちの創造的探求を続けていったのではないかと想像されます。AIと人間のコラボレーションによって新たな芸術の可能性を模索し続ける姿が想像できます。
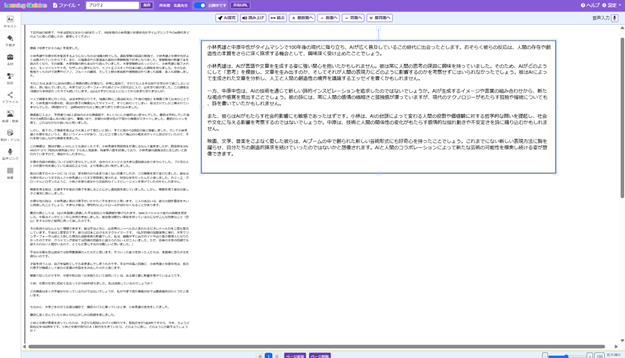
すごすぎる。
でも考えてみようっと!
それで読み返して、考えたのですが、小林秀雄は、AIの文体に、興味を持っただろうか?
多分否定的だと思う。なぜなら、かれは、文体を通した生身の人間の魂に興味があるわけで、人工で作られた文体には興味なかったと思います。AIではなかったが、そういう批評がどこかにあった気がします。
中原中也に関しては・・・その気持ちを想像すらできません。中原中也の詩魂を理解するには、あまりに僕は歳をとりすぎ、感覚は鈍感になってしまったので。