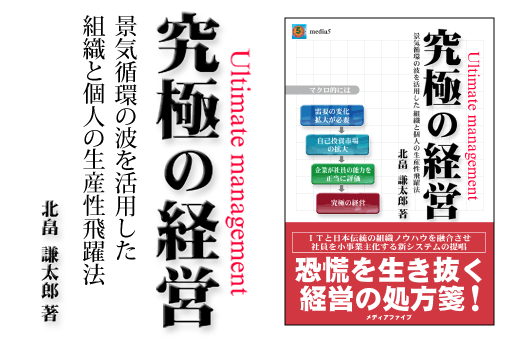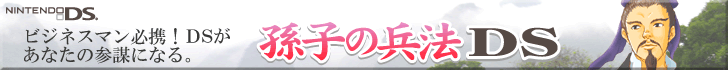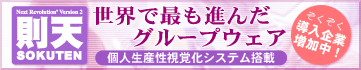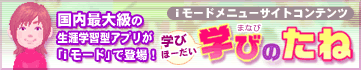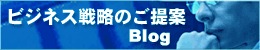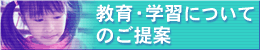ユラ・ハラリは、またセンセーショナルな本を出しました。「NEXUS 情報の人類史」です。この人は、「ホモサピエンス全史」「ホモ・デウス」と人類の指針となる本を出してきました。
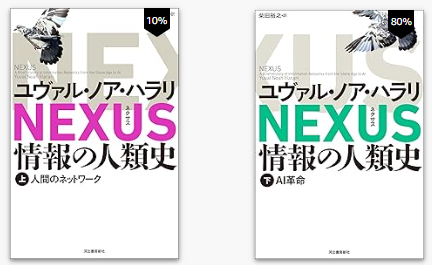
どれもとても重要な本ですが、今度の「NEXUS 情報の人類史」は我々の生活そのものに影響する、現存する最も重要な本というしかありません。
結論からすると、このAIの社会の浸透は、人類を破滅に導く、ということのようです。
じゃあ、AIを使うのをやめよう、というのは、不可能です。もう後戻りはできません。
なにか対策はあるのでしょうか?
このような問いかけを通じて、私たち自身が「考える」という訓練を日々積み重ねていくことが、これからのAI時代を生き抜く唯一の力になります。ハラリが『NEXUS』で危惧しているのは、情報をすべてAIに委ね、人間が「判断停止」に陥ることです。無批判にAIの答えを受け入れれば、そのAIを操るプラットフォームや政府、企業によって私たちの自由や意思決定が奪われかねません。
教育とは、まさに「問い続ける力」「判断を保留して多角的に検証する力」を鍛える場です。AIはあくまで道具であり、答えではありません。正しい問いを立てる主体性や、違和感やリスクの兆候をキャッチする感性、自分の言葉でものごとをとらえ直す力。これらを育てる教育が、いまほど必要な時代はありません。
AIの台頭は脅威であると同時に、学びのあり方を根本的に見直すチャンスでもあります。AIのまやかしを冷静に見抜く批判精神を、一人ひとりが身に付けること。それを支える教育こそが、ハラリの描いた「AIによる人類の悲観的未来」を乗りこえる唯一の希望です。
子どもも大人も「知る」ことの喜び、「自分で問い、考える」ことの大切さを学び直す時です。私たちが教育を再定義するとき、AIの時代も人間の自由な思考と創造性が灯り続けるはずです。
人類ひとりひとりが、AIをうのみするのではなく、出してきた答えに、いろいろな角度から分析し、AIのまやかしや、からくりを見抜く力を養うことです。もちろんAIをうまく活用して、より高度な知的レベルを獲得することを学ぶことは言うまでもありません。
たとえば、当社のツインAIシステムは、まさに、そういう目的で開発されました。
AIで出した答えに関連する情報や動画を集める機能がついてます。
さらに定例文でそのAIの解答の反論を示すAIを出すことも必要です。
「このAIの解答の問題点をしてして」
とか
「このAIの解答の反論を述べて」
とかです。
このような仕組みは、「唯一絶対の解答」に依存しがちなAI時代の教育にこそ不可欠です。自分が得た知識の根拠を探し、別の角度から比較し、反論を立ててみる――ツインAIシステムのようなツールは、まさに批判的思考のトレーニングを助けます。これからの教育現場は、「正答を素早く出す力」よりも、「なぜそれが正しいのか/正しくないのかを問い直す力」を養う場所へと変化していくでしょう。
AIによる情報は膨大ですが、その中身や背景、そして隠された意図を見抜けなければ、本当の意味で「知る」ことにはなりません。ハラリがNEXUSで描いたように、私たちはAIと共存する宿命にあり、AIの進化を止めることも、過去に引き返すこともできません。しかし、教育によって「情報を鵜呑みにしない目」と「新しい問いを生み出す力」を持つ人間が増えれば、AIがもたらす危機的未来を希望の未来へと変えていくことが可能です。
大事なのは、AIに支配される側で終わるのではなく、AIを理解し、活用し、人間が主体的に「選択する」知恵を持つこと。そのためには、一人ひとりが日常の中で問い、つながりを探し、対話することがこれまで以上に求められます。
私たちは教育によって、思考停止ではなく思考深化の道を歩まなければなりません。自分の頭で考え、疑い、議論しあうことで、AI時代を「人類の成長と自由の時代」に変えていきましょう。
AIと教育―この二つをどう結びつけ、どう使いこなすか。その意識が、私たちの未来を決める鍵なのです。