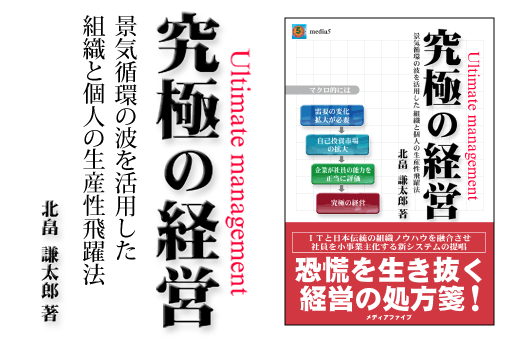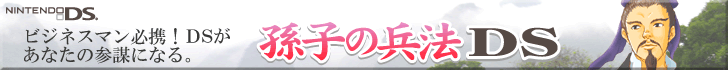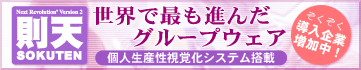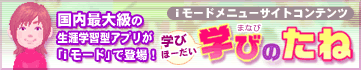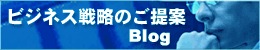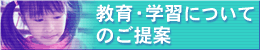今年、226事件が起きて89年になります。
226事件は1936年に起きました。
三島由紀夫が11歳のときでした。
三島事件は、1970年に起きました。
私が10歳のときでした。
三島が11歳の時の226事件の体験談をどこかで読みましたが、
自分が三島事件を小学四年生の時テレビで見た感覚とどこか共通してる、
と感じました。
226事件は、日本の軍部が政治に深く関与し始めた時期に起きた重大な事件です。
根本原因
1. 経済的不安、昭和恐慌による桁外れの経済的困難が背景にありました。農村部の貧困や失業率の高さが社会不安を増大させました。
2. 政治腐敗と不信、政治家たちの腐敗と政策の不透明さがあったため、国民や軍部は政府に不満を募らせていました。
3. 軍内部のイデオロギー対立、陸軍内では、天皇親政を望む革新派(統制派と皇道派)と、その手法に異を唱える勢力との間で対立がありました。青年将校は強硬な改革を志向する皇道派の影響を受けました。
結果
政府高官の暗殺 高橋是清大蔵大臣、斎藤実内閣総理大臣などが暗殺され、一時的に政府の機能が麻痺しました。
クーデター失敗 青年将校たちの動きは最終的に失敗に終わり、多くの首謀者が処刑や重罰を受けました。
政治への影響
1. 軍部の影響力強化 事件後、政府と天皇制に対する軍部の影響力がむしろ増す結果となりました。軍部が政治的な影響をさらに強めていくきっかけとなりました。
2. 統制派の台頭 陸軍内でより現実的な統制派が勢力を伸ばし、組織としての結束や政治的な影響力を高めました。
陸軍組織の欠陥
1. 上下関係の不明確さ 当時、陸軍内では若手将校の自主的な行動がしばしば許容され、組織的な統制が弱かったことが、こうした事件につながりました。
2. 教育の偏り 陸軍士官学校での教育がイデオロギー重視であり、政治的慎重さや法の尊重が欠けていました。
3. 内部対立 陸軍内での派閥対立が激しく、組織内のまとまりに欠けていたことも影響しました。
なによりも、明治維新以降、日清戦争、日露戦争で、日本は、奇跡的に大国に勝ち、
日本国民そのものが軍人を過度にリスペクトし、最終手段は、戦争で解決すればいい、という雰囲気が国内に蔓延したいたようです。
陸軍士官学校も、海軍士官学校も帝大以上に難関と言われ、青年将校は最高のエリートとして将来を嘱望されていました。
2.26事件は、政治を暴力で動かす結果となり、米国との開戦に、歯止めをかける政治家がいなくなった要因にもなりました。
昭和天皇独白録では、昭和天皇は、太平洋戦争の開戦を止められなかったのは、もし止めていたら、自分は暗殺され、さらに国家は収集がつかないものになっていたであろう、と証言しました。
実際、2.26事件の首謀者安藤大尉は、クーデターにより、自分と仲が良かった秩父宮を立てようとしたようです。
昭和天皇が、2.26事件の勃発で、激怒したのは、そのことが念頭にあったと推察されます。
大きな組織にいると、派閥などの政治力で動くこと組織が古くなるほど大きくなります。
そもそも国力が米国の10分の1しかないのに、開戦時には、陸軍が北進して、中国やロシアと戦い、海軍は南進して、イギリスやオーストラリアなどと戦いながらの開戦では、どんなに大きい国家でも勝てるものでも勝てません。
組織は70年で劣化すると言われています。1917年に革命で生まれた
ソビエト連邦も1987年に崩壊しました。
中国共産党も1948年に中国本土統一して、2018年ごろから行き詰り始めました。
日本もすでに戦後70年です。
組織の劣化が派閥争いや、組織内論理で行動するようになり、70年で亡ぶのです。
組織の劣化こそ、AIによって防げるのではないか、と考えます。
次回はそのことについて話します。