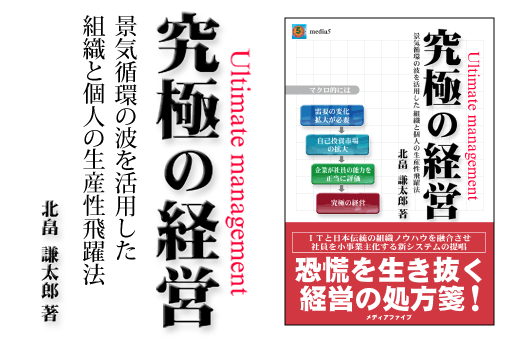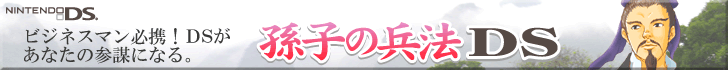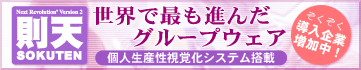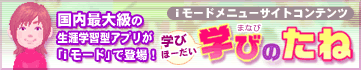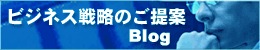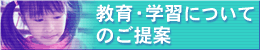なぜ、2.26事件で青年将校たちは、あのような暴挙をおこしたのでしょうか?
世界恐慌が始まり、冷害も重なり、東北地方では、娘を身売りする親が続出していました。
当時、徴兵で駆り出される兵隊は、農家の次男三男が多く、部下より青年将校たちは、地方の惨状を聞いていました。
青年将校は、政治が、外国や財閥からの賄賂をもらった老獪な政治家による政治がその原因と信じ込み、当時の岡田内閣の閣僚を暗殺していきました。
まあ、近衛文麿のブレーンである尾崎秀美がゾルゲ事件で昭和41年に逮捕され、処刑されたことを考えると、現在の政治状況と近いものはあったのでしょう。
米国でも、財務次官補のハリーホワイトなどソ連のスパイだった官僚や政治家も多く、戦後マッカーシーによる赤狩りが行われたほどでした。
事件の前年、226事件の幹部の一人、安藤輝三大尉は、当時、天皇の侍従長であった、鈴木貫太郎に東北の農村の惨状を直談判しに行きました。その時、安藤は鈴木の人格に感銘して、西郷隆盛のような人だ、と言ったそうです。
高橋是清は、近現代で最高の政治家であり、最も私信の少ない政治家なのに、軍備予算を削減したことで、青年将校の刃にかかってしまった。先日小金井公園にある移築された高橋是清邸に入って感動しました。大河ドラマ韋駄天で、ショーケンが、高橋是清を演じ、まさに遺作となったシーンなのですが、まさにそのシーンは、ここでロケをしたのを覚えていました。



組織は、モチベーションやプライドが高ければ、高いほど、反動としての不満も高くなる。
226事件は、日本の陸軍の若手将校たちが1936年に引き起こしたクーデター未遂の出来事です。これは大きな組織内での「派閥争い」の一つの例です。以下に簡単に説明します。
1. 指導層と下層の断絶
当時、若い将校たちは上の人たち(指導層)が何を考えているのかを理解できず、信頼関係が築かれていませんでした。普通の組織では、指導者とメンバーがコミュニケーションを取り合い、信頼し合うことが重要ですが、その関係が壊れていたのです。これにより、若手将校たちは自分たちの思いを実現しようと強引に行動しました。
2. 組織文化の欠如
陸軍の中に、きちんとした価値観や文化が育まれていなかったため、若手将校たちは暴力に訴えることが許される雰囲気を作ってしまいました。組織の内部での士気や倫理感が低下してしまい、暴力行為を正当化してしまったのです。
3. 合意形成の不在
組織では、みんなが意見を出し合い、合意を形成することが大切ですが、この事件ではそれができませんでした。特定のグループが自分たちの理想を無理強いして、他の意見が無視されるような状態になりました。結果、結束が失われてしまったのです。
4. リーダーシップの分散
組織の中で誰がリーダーかがはっきりせず、各将校が自分勝手に動くことが許されました。これにより、組織全体としての方向性が見えなくなり、最終的には分裂を招く結果に繋がりました。
5. 外部環境への適応力不足
226事件は、当時の日本が置かれている国際的な状況や時代の流れにうまく適応できていなかったことも影響しています。組織が外の環境に目を向けず、自分たちの内部問題ばかりを考えることで、外部からのプレッシャーに対処できなくなりました。
226事件は、組織内部のコミュニケーション不足やリーダーシップの欠如、文化の不在などが重なり合って引き起こされたもので、現代の組織にとっても重要な教訓があります。全員が協力し、意見を尊重し合うことが、強い組織を作るためには不可欠です。
さらに具体的に説明すると
226事件は、1936年に日本の陸軍の若手将校たちが政府を転覆しようとしたクーデター未遂の出来事です。これは、当時の政治情勢や軍の内部事情が絡み合った複雑な背景を持っています。以下に、事件の前に起きた満州事変や石原莞爾の影響についても含めて、説明します。
1. 満州事変とその影響
満州事変とは、1931年に日本の軍隊が中国の満州地域を占領した事件です。この事件は、石原莞爾という若い陸軍の将校が主導的な役割を果たし、自分たちの判断で行動しました。彼はこの行動によって英雄視され、多くの若い将校たちが彼のように、軍の力で国を動かしたいと考えるようになりました。これが、下層の将校たちの「自分たちの手で政治を変えたい」という気持ちを高める要因となりました。
2. 指導層との断絶
226事件が起こる頃、若手の将校たちは上司や政府の指導層と距離を感じていました。彼らは、政治の決定に参加することなく、ただ命令を受けるだけの立場であったため、憤りを感じていました。このような不満が彼らの行動につながりました。
3. 組織文化の変化
満州事変を経て、若手将校たちの間に「軍の力が最も重要」という価値観が育っていきました。このため、暴力的な手段がとられても許されるという雰囲気が生まれました。彼らは、意思統一や合意形成を無視し、自己の理想を実現しようとする傾向が強くなりました。
4. 合意形成の欠如
226事件の計画には、多くの若手将校が参加しましたが、彼らの間にもしっかりした合意はありませんでした。政府をどう変えるか、どのように行動すべきかについて、それぞれの思いが異なっていました。強い仲間意識はあったものの、具体的なビジョンが欠けていたのです。
5. リーダーシップと適応力の不足
事件を起こした若手将校の中には、リーダーシップを発揮する者もいれば、各自が好き勝手に動く者もいました。リーダーが一人ではなく、組織内での役割分担が曖昧であったため、全体としての方向性が見えなくなってしまいました。また、国際的な情勢や世の中の変化に適応できず、自分たちの内部問題ばかりに焦点を当てていたことも、大きな問題でした。
226事件は、満州事変の影響で生まれた若手将校の英雄視や、内部のコミュニケーション不足、リーダーシップの欠如、組織文化の不在が重なって引き起こされたものです。この事件からは、組織におけるコミュニケーションやメンバー間の信頼、リーダーシップの重要性が学べます。全員が協力し、意見を尊重し合うことが、強い組織を作るためには不可欠です。
組織におけるコミュニケーション不足やリーダーシップ、合意形成の欠如は、いつの時代でもどんな組織でも起こります。これをAIを活用したグループウエアが存在すれば、ある意味、こういう組織の劣化や誤解に基づく悲劇はおきなかったと思います。
次回、どういうシステムがあれば、このような悲劇が生まれなかったかを説明します。