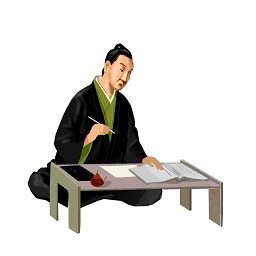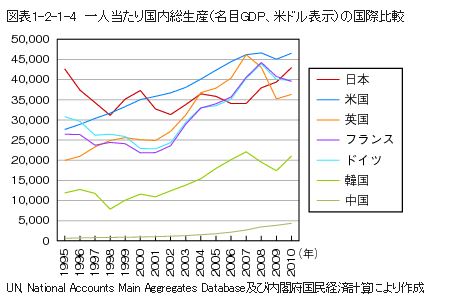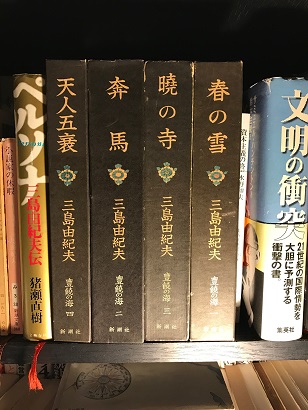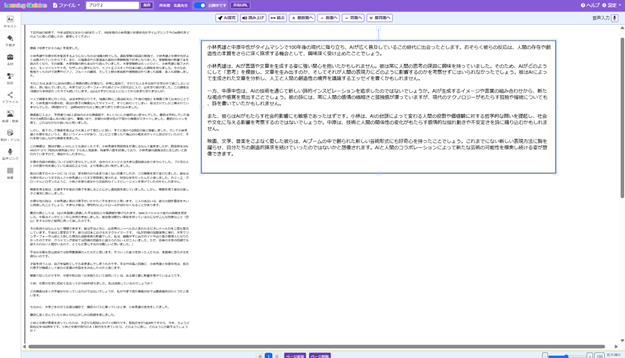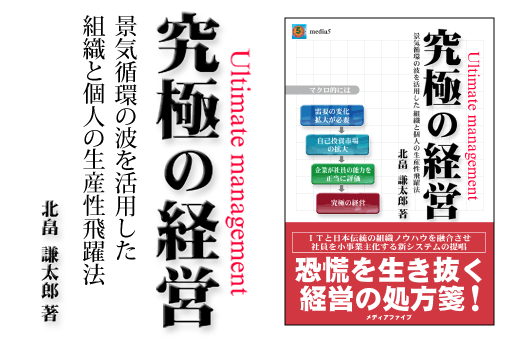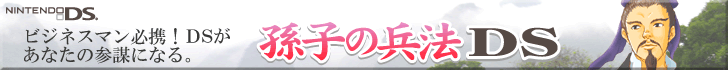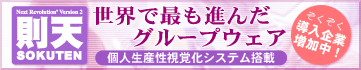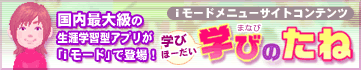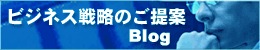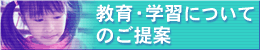「シェイクスピアとデジタル社会」
「シェイクスピアとデジタル社会」
シェイクスピアの戯曲は非常に現代性をはらんでいます。一つは人間性の本質を的確に表現しているからです。二つ目はシェイクスピアが生きたエリザベス女王時代は宗教の圧力も比較的少なく、比較的人間性を謳歌できる時代だというのもあるでしょう。女王の父が離婚問題でローマ教会と絶縁したため、当時のイギリスは中世キリスト教の呪縛から解放され比較的自由な時代でした。その中でちょうどルネサンス期にレオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロを輩出したようにシェイクスピアはヒューマニズム溢れる劇作がのびのびと行えたのでしょう。
会社などの組織に滅私奉公するのを価値とする宗教から解き放たれた今日、私たちはリセットするような気持ちで、人間性を見つめることを求めているのではないでしょうか。パソコンやインターネットは決して人間疎外をもたらすものではなく、人間の孤立を助長するものでもありません。人間疎外は組織に人を組み込む工業化社会のもたらした弊害であり、個人でも生きやすい情報化社会は人間性の回復が起こるのです。組織に従属されることにより、時間と金に拘束されてきた現代人は、携帯電話や電子メールでより密なコミュニケーションがとれるようになってきました。今、現代人は人とのコミュニケーションを回復させ、無意識のうちに自分を内省しはじめ、人間回帰の時代が始まろうとしています。
日本では、戦前は四書五経を語れなければ、いっぱしのビジネスマンとして認められなかったそうです。欧米では今でもシェイクスピアを語れないと一人前のビジネスマンとして扱ってくれない、いう人もいます。
ここで紹介させていただくのは、シェイクスピアの歴史劇で、特に1300年代のリチャード2世からエリザベス1世の父ヘンリー8世までのばら戦争を主なテーマにストーリー展開します。
シェークスピア史劇紹介
リチャード2世 5幕5場 「満足」
リチャード2世「こうして私は人生のなかでさまざまな人間を演じるが満足することがない。ときには王になる。すると謀反が起きる。すると乞食になりたい、と思う。王位を奪われて乞食になると、貧窮に打ちひしがれて王であった頃を懐かしむ。また王になると今度はヘンリーに王を奪われる」
リチャード2世は10歳にして王位を継ぎますが、おじのジョン・オブ・ゴードンが権勢を振います。フランスとの100年戦争の疲弊から有名なワットタイラーの乱など多くの暴動が相次ぎます。成人したリチャード2世は、なんとか権力を自分に戻そうとしますが、その一貫性のない裁定が周囲の信望を低下させます。ジョン・オブ・ゴードンが死に、リチャード2世はその土地を取り上げ、息子のヘンリーを追放しようとしますが、ヘンリーは兵を挙げ、謀反を起こします。リチャード2世はあっけなく敗れ、ヘンリー4世に王位を奪われ、ロンドン塔に幽閉されました。この独白はその時リチャードが語るものです。人は何もかも失い、信心を得て世の中を悟る。地位が高いときはその責任から逃れたいと考え、地位を失うとその貧しさから富の時代に帰りたいと考えます。満足とは満たされるものではなく、すべてを失って安らぎを得ることができると。
現代でもよく「金を払ってでも肩書きを外したい。」とぼやく管理職を見かけます。
かといって左遷や失職して、正月に来る年賀状の数が激減したりすると、たまらなく寂しさを感じるのです。富や地位、名声が上がればトラブルや問題が磁石のように集まってきます。逆説的に言えばトラブルや問題は自分が持っているものが多く、選択肢が多いのです。そしてすべてを失った時、その時の苦しみを忘れて、あの頃は良かったと思うのです。
ヘンリー4世 第1部5幕1場 「士気と名誉 1」
フォルスタッフ「おいハリー、もし俺が戦場で死にそうになったら助けてくれよ」
ハリー王子「そんなことできるのは巨人コロッサスぐらいのものだろう。早く観念して今のうちに神様に祈りを捧げることだ。お前の命は神様に借りているのだ」
フォルスタッフ「まだ返す時ではないだろう。期限も来ないうちに神様に命を返すなんてまっぴらごめんだ。なんでこんな危ない、厄介なことしなければならんのだ。名誉か?名誉なんて俺に取ったらなんの足しにもならない」
ヘンリー4世はリチャード2世の王位を簒奪し抹殺します。しかし国は謀反が絶えず、ヘンリー4世を助けていた片腕のホッパーが謀反を起こします。ヘンリー4世の息子ハリー王子の放蕩仲間フォルスタッフは、戦いを前にして、そのモチベーションとなる「名誉」について自問自答します。「名誉」は組織の意思の方向を決定し、士気を高める重要なファクターです。しかし集団の中にはフォルスタッフのように醒めた構成員が常に存在することを忘れてはなりません。構成員の下層へ行けば行くほど「名誉」という士気の道具はきかなくなるものです。大きい組織を動かすときは、下層の構成員を計算しないと効果的に動かせません。
ヘンリー4世 第2部1幕3場 「事業とリスク」
「春のはじめに膨らむつぼみを見て、秋の実りを期待するように、淡い期待は時として裏切られる。家を建てようとして設計図を引き、次に建築費用を見積もらなければならない。今度の仕事は一国をひっくり返し、新しい王国を建てようという大仕事だ。綿密に設計し、完璧に準備し、あらゆる障害を乗り越えられる能力と資力があるか検討すべきだろう」
ホッパーはシュールズベリの戦いで、父ノーサンバランド伯の援軍を期待しながら敗死しました。バードルフ卿は、それを例にとり、困難な状況では、最小の希望でも非常に大きな援軍に見え、ホッパーもかくして破滅の道へと飛び込んだのだと説明します。ヘースチングズ卿が「その状況に見合うモデルを立てれば期待も不都合なも のではない」と言ったのに対し、バードルフ卿は「シミュレーションは基礎を固め、財力と費用を計りにかけて計算することが最も重要である。事業計画を立てる時、現在の環境の基礎固めや現在の財力を慎重に計画することが侮られがちである。そして期待ばかりが幅をきかせる甘い事業計画になり、結局は失敗することが多くなる」と事業計画の極意を述べます。
ヘンリー4世 第2部3幕1場 「未来の予測」
ヘンリー4世は弟のようにかわいがっていたホッパーの反乱を押さえたのもつかの間、自分を王座につけた立役者であるノーサンバランド伯にも裏切られ、不眠に悩みました。
彼はなぜ予見できない悪いことが現実に起こるのだろうかと嘆きます。それを受けてワリックが「人間の生涯は歴史の書物であり、それをよく観察すれば未来を見通すことができます。先の王リチャードを裏切ってあなたは王になったのだから、あなたの腹心があなたを裏切るのは必然の結果である」と、ヘンリー王を諭す。未来の方向性を見定めるとき、現代だけを一生懸命分析しても見誤るだけです。過去を調べ、現代を観察することによって未来は見えてきます。
ヘンリー5世 4幕3場 「士気と名誉 2」
ウェスモランド伯爵「今ここに無傷の一万人の本土の兵士がいてくれればどんなに心強いことか」
ヘンリー5世「それはちがうぞ、伯爵。もし戦士する運命にあれば我々だけで十分だ。もし勝って生き残るのならば、少なければ、少ないほど名誉の分け前は大きいではないか。」
フランスとの戦いで、圧倒的な敵兵の数を見て、思わず「あと1万人ほしい」ともらす部下がいました。それに対し、ヘンリー5世は「味方が増えたら、名誉の大きさが減る」と叱咤します。「少数の人間で目的を達成すれば一人一人がより大きな名誉を手に入れることができ、その人たちは兄弟になる。」という。
これはベンチャー企業的な組織論です。
ヘンリー5世 4幕8場 「法」
ヘンリー5世はフランスとの決戦の前夜、一兵卒に変装して兵士たちの様子を見回りました。そのとき、兵士のウイリアムが、変装した一平卒を王とは知らず侮辱しました。王は怒り、戦争が終わったならば決闘する、という約束してその場から去りました。さて戦争が終わり、ヘンリー5世はウイリアムに身分を証し、自分への侮辱をどう償うのかと問いつめた。そのとき、ウイリアムは平然と「あの夜の相手がたとえ王でも、身分を隠していたのだから、自分は法を犯していません」と主張しました。その主張に納得してヘンリー5世は彼を許し、手袋一杯の金貨を与えたのです。たとえ王といえども身分を隠せば、一兵卒の扱いになる、という徹底的な法遵守の考え方は孫子の兵法の「法」の精神に通じるものがあります。
リチャード3世は戦死する。
リチャード3世 1幕1場「平時と非常時のリーダー」
長い薔薇戦争は赤い薔薇側のヨーク家が勝利し、容姿端麗な兄のエドワードが王座に就きました。後のリチャード3世、弟のグロスターはランカスター家との戦いの日々では、存在価値が大きかった自分が、平和の時代が来ると、居場所を持たないのに気づきます。そこで兄のエドワード王と次の兄のクラレンスを倒し、自分が王座に就こうと企みました。安定した時代はバランスのとれた毛並みの良いエリートがリーダーとなり、変革の時は異端児がリードして体制をひっくり返す。いつの時代でも平時と非常時のリーダー像はエドワードとリチャードのように対象的です。非常時のリーダーが平時で地位を保つのは難しい。ナポレオン、ヒトラー、織田信長、西郷隆盛はその典型といえるでしょう。
リチャード3世 5幕3場「戦わずして負ける」
孫子の5つのキーワードの一つに「天」というのがあるが、その「天」の一つであろう気、運勢を呼び込むことも重要な戦略です。リチャード3世は兵力では圧倒的に有利でした。にもかかわらず戦争の前夜、野営のテントでリチャードが寝ていると、亡霊が出現しました。彼は気が動転し、状況は一変した。悪の限りを尽くし、策略をめぐらし、地位を獲得しても、そこに正当性がなければ、気や運を呼び込むのは難しいものです。
これは「天」に逆らって戦う前から負けてしまっている人間の独白です。ビジネスでもリーダーの姿勢は常に顧客に対しては誠実であり、社員に対しては正義を貫く姿勢が大切です。濡れ手に粟の商売をしたり、社内に派閥を作ったり、不公正な人事はどんなに自分の立場が強くても、いずれは崩壊の憂き目を見るようです。正義や誠実さは隙を作らず、前向きの姿勢が運を呼ぶのでしょう。正義と誠実は比肩するもののない最高の戦略なのです。
リチャード3世 5幕3場「戦わずして勝つ」
リッチモンド伯、後のヘンリー7世はリチャード3世との戦いの前夜、はればれとした明るい気持ちで部下と戦略を討議していました。自分の正当性を信じ、前向きな明るく余裕のある状況は、リチャード3世とは対照的です。兵の数では不利でも運勢が見方しているので、悲壮な暗さはみじんもない。運気を追い風に、つまり「勢い」に乗って一気に決戦を挑もうという「人事を尽くして天命を待つ」状況はすでに戦わずして勝つ状態なのです
ヘンリー8世 3幕2場「失脚」
「ヘンリー8世の側近で、大変な権勢を誇っていたウルジーは失脚し、彼の片腕のクロムウエルに、こう言い残した。
「のう、クロムエル、聴いてくれ。わしが忘れられて……冷たい大理石の墓の中に眠ることとなったら……そうなれば、もう、わしの噂をする者は全くいなくなるに相違ないが…わしの失墜した理由は、わしの破滅を招いた理由によく注意しなさい。クロムエル、野心は必ずお捨てなさい。 自分を愛することは最後として、我を憎む者共をも可愛がるようにしなさい。常に右の手に寛厚な平和を携えていて、悪意の毒舌を黙らせるがいい。正を守って、恐れるな。もしわしが、王に仕えた其半分だけの熱誠を以て神にお仕えしていたのであったら、神はよもやこう年老いた今となって、わしを裸身で敵中へお見放しになるようなことはなかったろう」
ヘンリー8世の寵臣であったウルジーは、私欲を肥やしたことが王に発覚し、失脚する。
すべてを失ってはじめて悟ったことを部下のクロムウエルに伝えます。「なあクロムウエルよ、野心は必ず破滅を招き、買収は長い目で見れば正攻法以上の効は奏さない。神を信じ、正直にいきることが、長い目で見れば成功への近道であった」正義と誠実が最高の戦略である、と先ほど述べました。