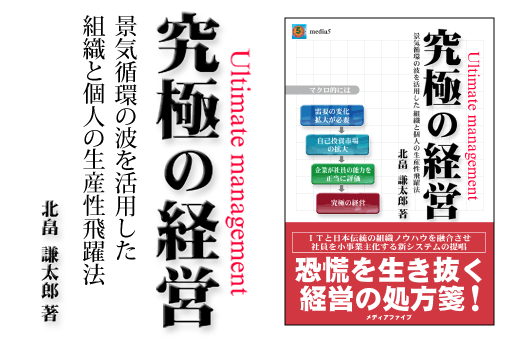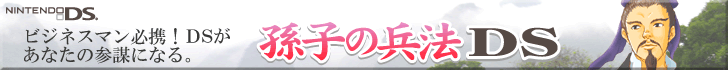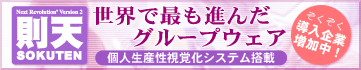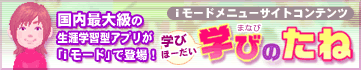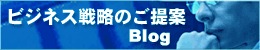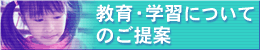今年の正月、たまに放映されるお能を録画するために、ビデオデッキを買いました。
今は、スマフォで録画予約から再生までできます。
そんなことから、時間を持て余す電車の中で、スマフォでテレビの録画予約をします。
また録画したものを、スマフォやタブレットでベッドの中や、wifiのつながるところでちょくちょく見ています。
いままで、あまりテレビや映画を見る習慣がなかったので、世の中の有名な映画を結構みるようになりました。
なぜか、最近は渥美清のドラマ、ドキュメンタリー,男はつらいよなどがよく放映されています。
男はつらいよは,渥美清が死ぬまで、48本も作られました。
まさに国民的映画です。
大学浪人のころ、恒例のお正月のテレビ番組で、この寅さんを見て、はじめて組織に属さない自分を同化し、面白い中に、寂しさを感じたのを覚えています。
高度成長期から平成の初めまで、石原裕次郎や加山雄三などの青春路線,高倉健や菅原文太のアウトロー路線、森繁久彌やクレージーキャッツ、そして渥美清に代表されるお笑い路線と、国民的映画はこの三つ巴でありました。
急拡大する日本経済の中で、裕次郎や加山はスマートに成功するおしゃれな勝ち組,やはり経済成長を裏稼業で稼ぐアウトローに比べ,寅さんは不器用で、そういう経済成長から取り残される下町の、本当に日常にあるような可笑しくも、ちょっと寂しい人情劇です。
今日ある勝ち組のオピニオンリーダーが、ユーチューブで講義をしているのを見ましたが、100万人の頂点に立て,という話です。
でも、クラスでもなかなか一番になれないのに,会社でもなかなか一番になれないのに,100万人の頂点に立つなんて、ほぼ100パーセントできないですよね。
でもリスナーは元気になるそうです。これは、僕はまやかしだとおもいます。
ひとはなかなか勝ち組にはなれない。でも寅さんのようにはなれるかもって思います。
おとこはつらいよは、1969年からはじまり、渥美清がなくなる1995年までじつに26年続きました。
どんなに社会を一世風靡したように感じても、石原裕次郎の青春ものも、1957年から67年くらいまでの10年、高倉健の任侠ものも1963年から70年、菅原文太のトラック野郎にいたってはたった5年程度です。
男はつらいよに続くのは、1981年から2001年までのドラマ「北の国から」の20年でしょう。
ヒーローものより、一般の等身大の人の映画がスーパーロングランになるのでしょう。
先日、あるユーチューブに100万人に一人になれ、というある先生の啓蒙ビデオを見ましたが、100万人に1人になるには、100万分の1、つまり、不可能ということじゃない、と思いました。
そういう啓蒙のしかたはあまり賛成できません。
そういえば、高校生のころ、トルストイが、小説でも音楽でも劇でも英雄や王侯貴族の芸術は新の芸術じゃない、等身大の民衆のなかから出てくる芸術こそ、もっとも価値がある、ということを言っている芸術論を読んだことを思い出しました。
ああ、トルストイがいってるのは、フーテンの寅さんのことなんだ、と今思い至りました。
私も少しでも、そんな教材が作れたらいいな、って思う今日この頃です。