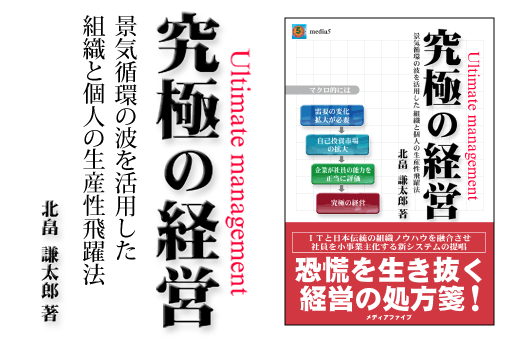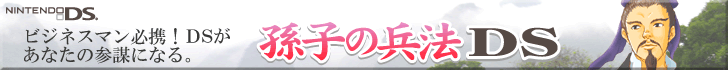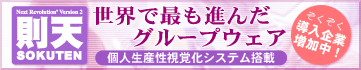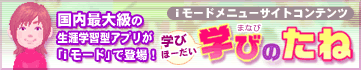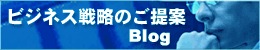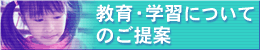富の再配分」について
企画営業部・田中 祥平
北畠社長と雑談の折、ひょんなことから「富の再配分」について愚説を披瀝したところ、早速、それを我がブログに書くべし、との命を受け、僭越ながら、述べさせていただく次第です。
この稿では、人間の歴史にとって、「富の再配分」という課題が如何に重要であったか。また、その解決法に如何にして人々は腐心してきたかを、簡潔に纏めたいと思います。いささか抽象的なお話しになることを、お許し下さい。
人間は、群れを作って生き抜いてきました。自然の猛威や獣害から身を守るため、或いは、他部族からの攻撃を避けるために。そのような共同体を「利益共同体」と呼ぶことにします。貨幣経済の発達した現代では、すべてが金銭価値に換算されます。しかし、物々交換が当たり前であったいにしえには、生きるための食料確保が、最優先されたことでしょう。
「利益共同体」の単位は、我が国では、日本国、都道府県、市町村、会社法人など様々な様式があります。そこにおいては、「富」という形で生きる糧となるものが集積されます。
我が国の歴史上、超有名人と言ってよい聖徳太子は、当時の大陸・朝鮮半島が絡んだ血みどろの争いを何とか解決しようと腐心しながらも、結局、各部族を融和させるには至らず、「夢殿」に籠もってしまったと言われています。六世紀から七世紀にかけての頃です。(現在、奈良・法隆寺にある夢殿は、太子の宮跡に再建されたものです。まだ法隆寺を訪れたことのない方は、是非一度、参拝されることをお勧めします。我が国初の世界文化遺産です。)
よく知られている「和をもって貴しとなす」と伝えられた太子の言葉は、僕には、問題を解決しえなかった太子の苦衷・心の叫びに聞こえます。
このような内乱は、幾つかの要因に分析できるでしょうが、「富の再配分」を巡って生じたものと見ることもできるでしょう。「富の再配分」とは、そのように戦争の原因にもなる重大な課題なのです。
聖徳太子は、解決策として「仏教」の導入を選択されました。この場合の「仏教」は、「システム」と読み替えたほうがいいでしょう。見方を変えれば、仏教の歴史は、そのような解決策を模索する過程であったと申せるかも知れません。解決策を別の言葉で表現すれば、「欲望のコントロール」ということになるでしょうか。
少し時代は下って、平安時代(八~九世紀頃)、弘法大師・空海が中国・唐からもたらした「鎮護国家(ちんごこっか)」という「法」(システム)がありました。そのシステムは、国を平安ならしめ、民の安寧を計る目的を持ったものです。広義には、「密教」と呼ぶことができます。これも、「富の再配分」を解決する方法のひとつと言えるでしょう。(京都・東寺を訪ねれば、その装置<システム>の一端をかいま見ることができます。)
また、鎌倉時代(十二~十三世紀頃)には、「絶対他力(ぜったいたりき)」を説く阿弥陀信仰が隆盛しました。簡単に申せば、現世における栄達や繁栄を諦め、来世での幸福を阿弥陀如来に全面的に委ねる、というものです。「諦める」ことで、無用な摩擦を避けて、争いの元になる「欲望」を押さえ込み、平安な状態を保とうとしたと思われます。それも、「富の再配分」という課題を解決するための欲望のコントロール法のひとつ、と言えるのではないでしょうか。
さて、人の「欲望」とは、何でしょう。生命体が本来持っている生存欲、子孫を残すという生命力そのものが、「欲望」の源泉です。そこから、食欲・性欲・睡眠欲などが派生すると見ることができるでしょう。つまり、生きるためには、「欲望」を全面的に否定することなど不可能ということになります。そこで、コントロール法が重要な課題となるのです。
それはさておき、少し話題がそれるのをお許し頂きたく思います。ITを宗教の歴史の中にどのように位置づけるか、というテーマです。何を頓狂なことを、と仰らずに、もうちょっと耳をお貸し下さい。
「ウェブ(インターネット)空間」と「仮想現実空間」に的を絞り、要点を整理してみます。
仏教には、この世に存在するすべては、網の目のように結ばれている、という考え方があります。それを「天網」と呼びます。密教に伝えられた曼荼羅(マンダラ)には、天網の考え方が、判りやすく図示されていると見ることもできるでしょう。ウェブ空間は、そのような天網思想の一部分を現実化したものと、僕は理解しています。
また、仏教には、「瞑想」(メディテーション)という技術(メソッド)が伝えられています。そのメソッドは、この世とあの世を含めた追体験法と言えるもので(あの世があるかないか、という議論は、ここでは措いておきます)、明確な映像・イメージを伴った方法です。「セカンドライフ」などの仮想現実空間は、そのような瞑想技術が、パソコン上で実用化されたひとつの事例と考えています。「マインドマップ」などの思考技術も、その延長線上にあるものと見ていいかも知れません。
つまるところ、IT時代における「富の再配分」という課題を解決するシステムのひとつとして、【Next Revolution】(仮称)が編み出された、と位置づけることができるでしょう。
最後に、重要なポイントに触れておきたいと思います。どのように優れたシステムでも、その運用次第で善にも悪にもなる、ということです。要するに、運用する「人」次第、というのが、システムが背負う宿命と言っていいでしょう。それは、人間の歴史が証明しています。