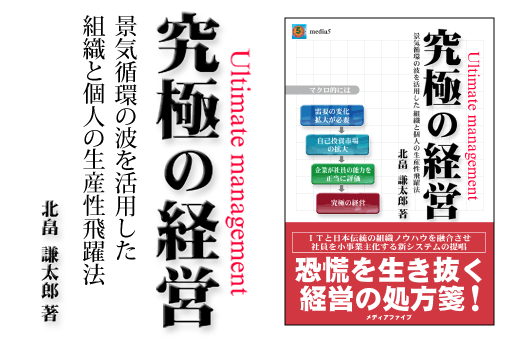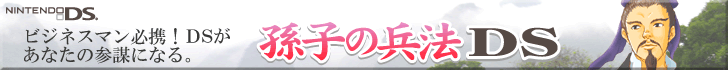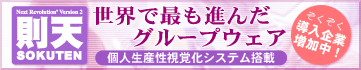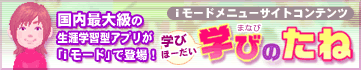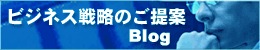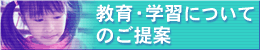光の君から武士の台頭 承久の乱 鎌倉滅亡 建武の新政 江戸幕府 明治維新 敗戦戦後復興 インターネットの普及 AIの普及
あけましておめでとうございます。今年は2025年、日本史においても劇的な年になることが期待されます。特にAIが仕事、教育、生活に大きく関わる年となりそうです。今回は、これらの出来事が歴史の中でどのように位置づけられるかを、昨年の大河ドラマ「光の君」を通じて考察してみましょう。
光の君の時代
奈良時代の終わりに平安時代が訪れると、貴族文化が隆盛を迎えました。その中心にいたのが「光の君」として知られる藤原道長です。道長は摂関政治を完成させ、天皇を巻き込む政治を展開しました。この時期、文学をはじめとする華やかな文化が育まれました。
しかし、奈良時代の終わりに起こった刀伊の入刀やその他の反乱が、貴族社会の脆弱さを露呈しました。藤原隆家は例外的にこれを防ぎ、活躍しました。
武士の台頭
平安時代の末期から、地方を中心に武士たちが力を蓄え、貴族社会に対抗するようになりました。源平合戦後、源頼朝は鎌倉幕府を開いて武家政権を確立しました。
承久の乱と鎌倉幕府の強化
承久の乱(1221年)は、後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対抗しようとした重大な戦いでした。鎌倉幕府はこれを制圧し、武家政権の力をさらに強化しました。中央での統制が強まり、武家社会の安定が図られていきました。
しかし元寇が起こると地方分権を主とする武士の統治への不満と不安が社会を蔓延しはじめました。
建武の新政と室町時代の始まり
その後、鎌倉幕府は1333年に足利尊氏によって滅ぼされ、後醍醐天皇は建武の新政を試みましたが、短命に終わりました。
理由は、最も大きいことは、元寇による外部からの攻撃があったからこそ、分権的な幕府政治が不都合だったのであり、元が弱体化し、滅亡したので、当面の外敵を心配しないことが主因でしょう。
次に、後醍醐天皇が、実の子である護良親王を自らの手で抹殺したことにより、ヨーロッパでは主流である貴族の武人化の目をつぶしてしまったことです。
そこで足利尊氏は鎌倉に替わり、室町幕府を開き、新たな武家時代を築きました。この時代は、経済や文化が新たな隆盛を見せる時期となりました。
しかし、尊氏は、南北朝時代、土地を分配することで武士を味方にすることで、室町幕府は権力を集中することができずに、日本国内の内乱は年を追うごとに増加し、第八代の足利義政の時代には、日本を二分する、応仁の乱を引き起こし、そのまま内乱が沈静化することなく、日本中が戦乱となる戦国時代へと突入します。
戦国時代は、織田信長を経て、豊臣秀吉が天下を統一し、このころになると、鉄砲の数も、戦士の練度も、おそらく世界一になっていたでしょう。信長も秀吉も世界へと領土拡大を狙っていたものの、果たせず、その生涯を終えました。
江戸幕府と安定の時代
徳川家康は1603年に江戸幕府を開き、長期にわたる平和な時代をもたらしました。家康は武器を農具などに転用し、穏やかな時代を築きました。
しかし、スペインは、当時の金と銀の生産量世界一である、日本の植民地化をなんとか実現させたく、豊臣家の後押しをして、大阪冬の陣、夏の陣を起こさせましたが、失敗しました。
その結果、鎖国政策が取られ、外部の影響を遮断し国内の発展に注力しました。江戸は世界2位のGDPと繁栄を誇り、文化や経済が全盛期を迎えました。
明治維新と近代化
平和な江戸時代も250年続くと、その幕藩体制も制度疲労を起こし、スペインにとって代わり、米国と英国、ロシア、フランス列強が、世界の植民地を求め、日本へも迫ってきました。
江戸時代の後、1868年に明治維新が起こり、急速な近代化が進みました。西洋の技術と制度が導入され、日本は強国へと歩を進めました。
日本は、富国強兵のスローガンのもとに、みるみる欧米列強に伍する力を蓄えました。それは、江戸時代こそ、教育立国を目指し、藩校から寺子屋まで、あらゆる国民が文字を覚え、四書五経を学び、士農工商という職分に分かれ、工夫をし、勤勉に働いた基礎があったこそでしょう。
その結果、日本は、清、ロシアという強大な国の戦争に勝ち、それは、日本国民に、軍事力さえ強力なら、あらゆる外交も思いのまま解決し、大きな豊かさを手に入れられる、という錯覚をさせることになりました。
日露戦争での勝利で、ポーツマス条約で、ロシアから、満州や樺太の権益を確保したものの、膨大な賠償金をとれなかったことは、日比谷焼き討ち事件など、大きな暴動を各地で起こしました。
しかし、国民のおごりと、日本の軍事力が最強という錯覚は、権益のある、満州で、満州国を建国し、上海事件や日華事変を起こし、軍部の暴走が始まりました。
その決定的な事件が2.26事件です。昭和11年2月26日、青年将校が首相官邸や閣僚を襲い、高橋是清、斎藤実、渡辺錠太郎など政府高官を殺害しました。この事件ののち、政治家や文官は表立って軍部に反対するものがいなくなり、米国により、石油を止められ、日本は追い詰められていくのでした。
昭和16年12月21日真珠湾攻撃により、日本と米国は戦争を開始し、国力が10倍以上異なる米国に次第に追い詰められていきます。米国との戦争の敗因は国力もありますが、日本の軍部の海軍と陸軍の派閥争いも大きく影響していました。
日露戦争の時は、まだ、当時の軍幹部に、明治維新の元勲が生存していたので、陸軍と海軍も連携ができていましたが、太平洋戦争は、その子息である2代目、3代目が陸軍と海軍の派閥争いに終始していました。陸軍は中国、ロシアとの闘いで北上し、海軍は米国との闘いで南進し、これでは、とても勝ち目のある戦争などできません。当時の最新兵器である飛行機の開発にも陸軍海軍ともに相手に情報を渡さずに、開発をしていたのですから。
東条英機は、ミッドウエー海戦で、海軍がほぼ主力艦を失ったことを、すぐには知らされませんでした。後日、戦局も行き詰ってから、それを知らされ、「それをしっていれば、あんな無謀なインパール作戦などしなかったのに・・・」といったそうです。
いまの政治もそうですが、2代目3代目が主流になると、組織での出世が第一で、組織が自己目的化することになり、国が亡ぶ要因になっていきます。70年というのがひとつの節目なのかもしれません。ソ連も1922年に建国して、1991年に崩壊しています。中華人民共和国も1949年に毛沢東が建国宣言して、2019年で70年です。戦後日本も1945年から起算すると2015年です。
敗戦と戦後復興
第二次世界大戦の敗北は日本に大きな試練をもたらしましたが、その後の戦後復興は驚異的なものでした。アメリカの援助を受けながら、工業化を進め、経済は奇跡的に回復し、高度成長期を迎えます。この驚異的な復興は、満州国の建国をモデルに戦後復興をすすめた、と言われています。
1964年の東京オリンピックと、新幹線開通、1970年の大阪万国博、1985年のつくば万博などを通し、日本は1968年にGDPは世界2位になり、2010年に中国に抜かれるまで、2位を維持していました。
1985年、米国は、双子の赤字など、日本の経済を脅威と感じ、プラザ合意でむりくり円高誘導へと導きました。日本は経済戦争でも米国に鉄槌をくだされたのです。それでも日本企業は従来の貯蓄と旺盛なイノベーションでなんとか91年くらいまでは、日本の活況は続きました。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」「Noと言える日本」など日本の経済力を賛美する本が、米国や日本ででたのもこのころです。
ただ、米国もそのまま黙ってはいません。苦境に陥た米国の巻き返しが、すさまじいのです。
まず手始めに米国が行ったのは、日本からの輸出の増加を止めるために、強引な政治的介入をおこないました。プラザ合意です。
プラザ合意は、円を円高に押し上げ、結果日本国内で生産することが不利となり、日本の大企業は海外へと製造拠点を移し始めました。特に、鄧小平の中国は、これから成長する巨大な市場であることを宣伝し、世界に工場を中国国内に移すことを、より推奨しました。
その結果、日本の大企業はこぞって、中国に工場を作り、グローバル化を進めました。日本は円高不況に陥り、より安いものが売れるようになり、ユニクロ、ニトリ、ダイソーなど中国で作ったものを日本国内で安売りすることで、脅威的な企業成長を実現し、業界を席巻しました。
その反面、日本の経済は、大企業の投資が止まり、労働者の9割以上の中小企業、派遣労働者の低賃金のせいで、市場縮小とデフレが30年も続き、大企業は、中国での投資のみを拡大し、ほぼ日本以外をターゲットとするグローバル企業へと変貌していきました。中国は中国国内に進出する企業に条件を付けました。それは必ず中国との合弁事業にすること、そして株式51%以上を中国企業が取得することです。
しかも中国で挙げた利益を中国の国外に持ち出すことはできず、中国国内で再投資しなければなりません。それが脅威的な中国の経済成長を実現させました。日本の大企業の社長は、現在、ほとんどの企業がサラリーマン社長です。好成績を残さないと株主総会で交代されられるので、確実に利益のあがる中国市場に固執する理由は、連結決算で、よりよい利益を数字上であげられることにあります。
インターネットの普及と情報革命
1990年代にインターネットが普及し、情報社会が加速しました。人々は情報にすぐにアクセスできるようになり、ビジネスや日常生活においてもその影響は計り知れないものでした。
中国も日本もそうだけど、需要創造は、どうしても簡単に大きなお金が動く不動産と金融が中心になります。価値創造という「お金」が、株や投機で空想の価値を生み出し、それを不動産という現物で裏付ける。日本のバブルを、中国は研究しつくしたにも関わらず、同じことを行ってしまいました。しかも10倍の規模で。
需要創造は、基本、2009年の丙著「究極の経営」で述べたように、個人も組織もナレッジによるイノベーションによる需要創造が作り出すことが健全な経済発展だと思います。
米国は、まずは、ウォール街で世界中の金を集め、世界中から天才を米国の大学に集め、そして軍事ネットワークを開放して、インターネットとして、情報を集め、ひっきりなしに大学中心に起業させ、ITと、金融と、軍事力と、そして農業も資源開発も、イノベーションを先導して他国の追従をゆるさない経済・軍事大国になりました。
そして実体経済が良かろうが、悪かろうが、株価を釣り上げて、1%の超富豪が、政治を、経済を支配しました。そして今日、次世代中心的な役割を担うAIまでも米国が握ったのです。映画Civil Warのような内乱が起きない限り、米国の一国巨大化は続くでしょう。
AIの普及と未来社会の構築
今日、AI(人工知能)は社会のさまざまな分野で普及しています。データの分析、医療、交通、エンターテインメントなど、多岐にわたる分野でその力が発揮されています。AI技術は、日本が直面する社会課題の解決に向けた新たな可能性を提供し続けており、未来社会をより豊かで効率的なものにするための鍵となっています。
このように、日本の歴史は多くの転機を経て現代に至り、技術革新がさらにその先の未来を築こうとしています。
日本の歴史は数多くの転換点を経て今日に至りますが、伝統と文化を重んじながらも、新たな技術を取り入れることが必要です。AIを活用した新たなイノベーションが、日本の発展に寄与することでしょう。